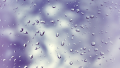高分子の膜(ポリマー)を使用したセンサは湿度センサとしての歴史が長く、主に湿度領域の水分の測定を得意としてきたセンサ構造となります。
原理は酸化アルミセンサに似ており同じくセンサにポーラス状の膜(ポリマー)の上下に導通する素材で挟み込み、ポーラス状の膜に水分の分子が入りことによって変化する静電容量の変化を水分量として計算しています。
ただし、酸化アルミセンサとの多きな違いは、構造上高湿度の水分領域への特性があるため湿度センサから露点センサへと発展してきた経緯がり、低湿度側の感度が弱い傾向にあります。
高分子膜の水分による静電容量の変化領域が高水分領域が得意だったこともあり、低水分(-60℃do以下)の領域においては、一部のメーカーの高分子センサのみー80℃dpまでの測定範囲下限までの測定に信頼性があるのでー60℃dp以下の領域へ使用する際には注意が必要となります。
特徴として、ポーラス構造部分がポリマーの為酸化アルミ方式に比べて均一な製造が可能なため水の分子の入りと出入り両方向が迅速に行われるために酸化アルミ方式より応答性と再現性に優れており、特にー60℃dpまでの応答速度に関しては、CRDS方式などの分光式に匹敵する応答速度を有しているメーカーのセンサもあります。
※一部のメーカーに露点予測機能を内蔵している機種があり、最新のバージョンは予測を外す確率は減ってきてはいるが、露点変化の状況によっては露点指示の変化が実際の露点よりずれる場合があるので、採用するアプリケーションによっては注意が必要となります。
※センサ部にヒーターで熱をかけてコンタミ混入状態でのゼロ点補正を行う機能内蔵の機種でも完全には補正しきれずにドリフトは起きる傾向にあり。
特徴
・精度 〇(-60℃までは〇、-60~-80は1部のメーカーのみ〇)
・応答性 ◎(-60℃までは〇、-60~-80は1部のメーカーのみ〇)
・再現性 ◎(-60℃までは〇、-60~-80は1部のメーカーのみ〇)
・耐圧力性能 〇(15Mpa耐圧対応まであ機種あり)
・測定ガス △(基本的に不活性ガスのみ。CO2ガスに関しては指示がずれる)
※一部のメーカーに有機溶媒対応機種あり、熱で溶媒を飛ばす機能内蔵
・耐腐食性ガス対応 ×
・防爆対応 〇(日本の認定はメーカーの直状況次第)
・コスト ◎
・ランニングコスト △(定期的な校正が必要)
・耐コンタミ性能 △(酸化アルミ方式より強い傾向にありますが、構造上ポーラス部分に入ると校正が必要)